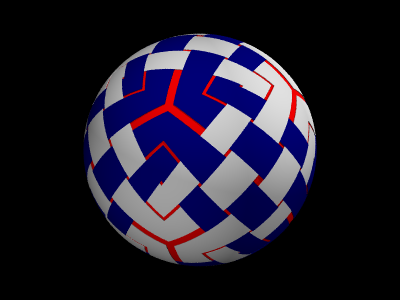びんてまり(その2)
びんてまり(その2)

過去の表紙85で、自作のびんてまりを紹介しましたが、
そのときの手まりは直径が11cmほどありました。
しかも 確か あのときは 手まりを作り始めてから、瓶を探していたような。。。笑
なかなか ちょうどいい瓶がなくって 困りましたね。
買い物にいく度に、何かちょうどいい入れ物はないか、
直径11cmくらいの球体が入る大きさで、透明で、入り口が狭いいれもの、、、
と常に物色していました。ほんとは もっと入り口の小さい瓶に
入れたかったのですが、そのときは仕方なくあの器にいれたのでした。
いま日付を確認すると、2004年の初頭ですね。
でもやはり処女作ということもあり、出来がいまひとつだという思いは
結構ありました。そういうわけで、その後、 もう一度作ってみよう、と。
次回は まず手頃な瓶を探してから作ろう、そして
もうすこし小さいものを作ってみようと思っていたのでした。
そうして、次のびんてまり用にちょうどいい瓶を見つけたのが、
多分 過去の表紙102を書いた2004年の夏頃だと思います。
んでもって、手まりのデザインは 過去の表紙102に紹介した「ねじり三角」に
しようということまで 決めたのでした。
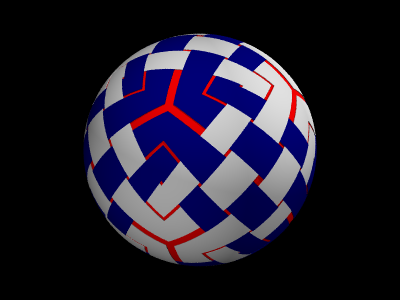 |
| ねじり三角 |
で、手まりを作り始めたわけですが、基本的な作り方は過去の表紙85で書いたのと
全く同じで、基礎となる赤い球体までつくり、地割りと呼ばれる目印になる
金糸を縫い付けるところまでやったところで、面倒になってやめてしまいました。笑
そうそう、そのときの地割りの刺繍は
まさにあそびをせんとやで
2005/10/18に
紹介されていた(図1)と同じです。この図1のラインは
多分 もっとも基本的な地割りだと思います。
正8面体群を基礎とする対称性の図柄の場合には、
まず必ずといっていいほど この地割りから始めるのではないでしょうか。
さて、そういうわけで、かなり長い間 作りかけの状態で放置されていた
のですけども、先日 とあるサイトを見ていたら、
なんだか 無性に びん手まりを作りたくなってきたのでした。

完成した手まり。今回の手まりは直径6cm弱です。
刺繍の巾を細くしたので、CGとは印象が大分違いますね。
でも、これはこれで気に入っています。
手前味噌なんですけども、今回は 前と比べても刺繍の丁寧さ等
随分とうまくなっている実感があって嬉しいです。(勝手に思ってるだけですが)
でも、あそこをこうすればもっときれいに出来るのかな、というところもあって、
いつかまた 作りたいですね。(実は瓶はまだある。)

できあがった「手まり」と「瓶」です。後は入れるだけ。

瓶に入れて、「びんてまり」の完成
 もどる。
もどる。